内容が古くなっている場合があります。
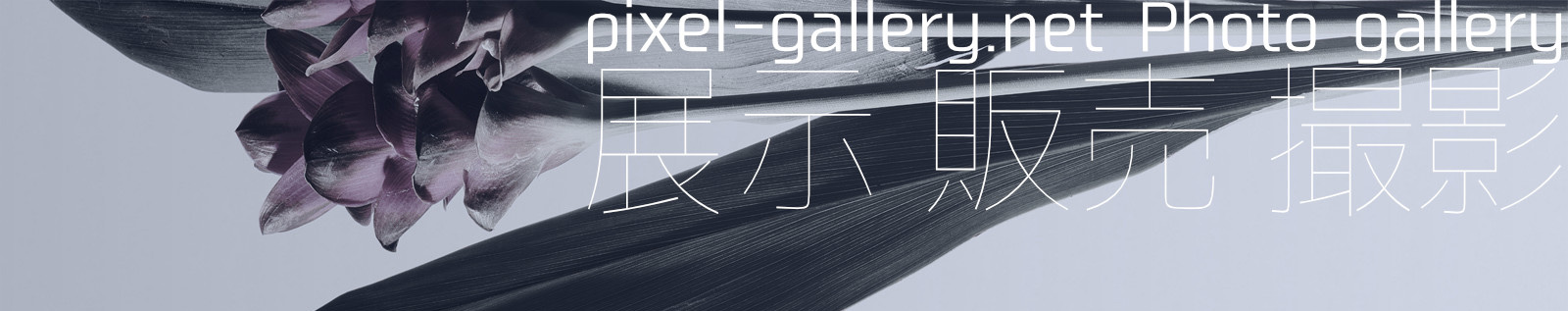
カメラを買って撮影しはじめたばかりは、どこへ行って何を撮っても、思い通りの結果でも失敗が多少あっても楽しいのだが、やがて誰かに「どれも同じ写真みたい」「何を撮っても同じ」などと囁かれてげっそりしてしまう人が多い。
そんなひどいことを言うのは家族だったり、なかには写真仲間が自分のことを棚に上げて評論家を気取ったりする。マンネリというかそれしか撮影できない、は恥ずかしいことなのかどうか。私からしたら何も恥ずかしくないし、むしろスタイルの発見につながる美意識の現れだと思う。
だから、マンネリにすらならないバラバラでちぐはぐな写真を量産していたり、テーマを絞って撮影しているのにこれといった一貫性がない写真ばかりの人から「どれも同じ写真みたい」「何を撮っても同じ」と言われたら、笑ってやればいいのだ。
私がどういう人間かは about🔗を見ていただければわかるし、私がプリントを売るため作成している作品はギャラリーサイト🔗に展示している。作品を見ていただければわかるだろうが、前述のような悪口が得意な人に言わせれば「マンネリ」であり、なかには数年間(それなりに変化しているけれど)テイストを継続させているシリーズ作もある。
なぜ、同じテイストを継続させるのか。美意識がテイストの方向性を決め、テイストを追求することで美意識の解決を目指しているからだ。一回やって何かに到達して、完成しきって、あとは惰性でしかないなんてことは滅多にないかありえない。古今東西、画家だろうと彫刻家だろうと工芸家だろうと写真家だろうと作家だろうと同じだ。
だから納得いくまで続けるし、こうした作品を買いたいという方がいるならテイストやスタイルへの「評価」にほかならないし、その方が買い求める作品をつくるうえでテイストを維持する場合だってある。
つまり美意識と商売、双方でテイストが一貫したスタイルを継続させている。他のご商売でも同じだろう。レストランのシェフがころころスタイルを変えるだろうか。長年営業していれば少しずつ何かが変わるだろうが、新しいメニューを考案するたび別人の作のように変えたりしない。
テイストの一貫性、スタイルの確立は自分が何を撮影して何を表現したいかと一体のものだ。一貫性がなくスタイルが確立できない人は、何を表現したいかわかっていない人、表現したいものがあってもどうしたらよいか実現できない人なのだ。
ただし、「マンネリ」に対して何によってマンネリなのか気づかなくてはならない。
同じテイストとされる「テイスト」は写真のどこに、なにから生じているか。被写体の選択、構図、露光値、明暗の比率等々、テイストとはどれも数値や比率など実在の条件で形づくられていて、やる気、情熱、根気、知識などは無関係である。いったい「テイスト」は何がどうなっているか結果か分析できないとスタイルへ昇華できない。分析できればテイスト・スタイルを実現する方法がわかるのだから、継続してテイストを追求して完成度を上げたり問題点をあきらかにしたりできる。
ざっくり実例を示そう。
かなり前からこういう静物を撮影している。そして2018年に至り、以下に示すような表現になった。単純化、構成への注力、動きまたは不動といった偏屈な好みで撮影する植物の静物だが、私にとって植物のポートレイトだ。
実際には多数の作品があるが一部を紹介する。

このサボテンの写真あたりから背景濃度の見直しをはじめた。また背景の濃度にある程度のばらつきを出すか、均一化するかも模索した。
テイスト、スタイルを決定しているものが何か、それはどのような数値か把握できているのでこのような見直しは難しくない。
単純化は主題にしている植物だけでなく背景にも徹底すべきだから、濃度は均一化したほうが余計な情感や曖昧な印象を醸し出さずに済む。情報を削りおとしたのだ。あとは濃度の最適化だけだった。
「美意識の解決」への道のりだ。

背景濃度の最適化は続く。

2018年中にはおおよそ方針が固まったが、まだ検証は続けた。

2019年後半から2020年前半に最適化の検証が終わる。この間にライティングも変えているが、この話については別記事で説明したい。





以上、静物作品のうち花をテーマにしたものを例に挙げた。これは海景や砂景をテーマにした作品でも同じだ。
こちらは比較的新しい作品から振り返る。海景や砂景のなかに、異なるシリーズが細分化されているためいくらかテイスト違いが列挙される。






こうした創作を続けながら、敢えて異なる作風に探りを入れてもいる。どの要素を逸脱させるか、数値的にどれくらい逸脱させるか、意味的にどれくらい逸脱させるかなどの模索だ。


ここに至るまで2016年くらいから2017年は手探りだったが、2018年から2019年に一応の完成をみた。こうなるとロケーションや光線状態が違っても、(もちろん写りに違いはあるが)一定の調子、雰囲気=テイストで表現することが可能になる。



模索は撮影時だけでなく現像時にも試行錯誤する。基調は同じで、どこまで何を逸脱させるか模索した結果のひとつが[Past Light]シリーズだ。かつて撮影した写真(RAWデータ)を元に別物に仕立てている。福島県の津波被災地および避難地域を取材した写真を再生成するところから[Past Light]シリーズははじまった。


後に、[Past Light]シリーズ用の新撮影を行うようになる。

[Past Light]の解釈に幅が出てくる。

さて、ここに至るには袋小路に迷い込む道や、物珍しい表現をしただけで終わった例が多数あるが挙げたらきりがないのでこの辺で紹介を終了する。
あるロックギタリストの名言に「ラジオから流れてくる音楽を聴いて母親が息子の演奏とわかるようなら、その演奏は正しい」という趣旨のものがある。
あなたの人となり趣味、性格、言動を表だけでなく裏まで知っている人に、あなたが撮影して現像した写真だと気づかせられたら大成功だろう。「あなたが撮影した写真だ」というのだから、あなたらしさがテイスト、スタイルに現れているのだし、写真ごとバラバラではなくとうぜん一貫している訳だ。
だからマンネリ万歳であり、マンネリに対して何によってマンネリなのか気づくことで、単なる反復から自分独自のスタイルが導きだせるのだ。

© Fumihiro Kato.
Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited. All Rights Reserved.































