内容が古くなっている場合があります。
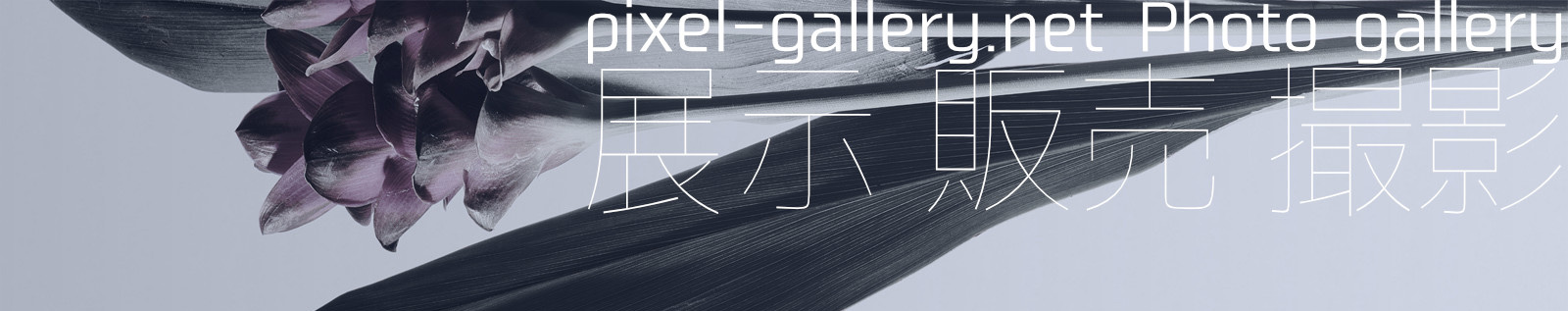
テーマ、作風(スタイル)を獲得するため写真を撮影して、獲得したもので撮影や現像を継続させる自転車操業は、創作につきもので宿命ではないだろうか。と、いうことでおいちゃんとの会話です。

最近、数年前の福島の写真を現像しなおしているよね。前の現像が気に入らなかったのか?




気に入らないというか、今ならこうする、こうしたいっていうとこかな。テーマがテーマだけに、どう撮ったらいいかわからないまま福島県に行って、けっこう悩みながら現像していたんだよね。ふっきれたというか。

いまのがバージョンアップした改訂版かな。

まったく新しいものとしたいところだよ、本人としては。

Past Lightっていうタイトルだし「光」を印象付けたいのかな?

浪江町とか相馬、南相馬に光を見たということなんだ。当時は、これをやりたかったのに振り返ってみると黒焼きというかドロドロの絵にしてたんだよね。なぜそうなったか理由はわかるのだけど、そうするほかなかった。そういうのを「ヤメタ、ヤメタ。言いたかったのは違うことだろ」と。
悪質な被曝デマを流す輩の嫌がらせが私生活に及んでいて、まあひどいありさまでね。気持ちが作品に漏れ出てしまってたんだ。

ああいう「光」の雰囲気って、どうして思いついたの?

砂丘や海を撮影していて、とにかく明るくする手法を見つけて、これを応用したとき何かはじまる気がしたんだよね。明るくといってもハイキーとも違って、眩しさとか現実を超越した心象というかを表してる。だからここ何年か続けてきたものからの応用ってことになるね。




テーマとか作風とか発生するときって、いつもこんな感じなの?

たぶん、そうだろうなあ。まったく別の意図や表現だったり、本来は一緒なのに別物と思い込んでいたりするものから、応用できそうで使えそうな何かがあると気づくというか。福島で撮影した写真を再現像して「Past Light」の発想が生まれて、これを自分のなかで使いこなして行こうと。

撮影段階から「Past Light」をやるぞと決め打ちしてるのか。まあ、そりゃそうだろうな。

そうやってガッチガチに自分を縛るとまさに自縄自縛に陥って、撮影と現像どっちも自分でも何やってるかわからんという馬鹿げた状態になるのよ。型に溶けた鉄を流し込んで同じ形の鋳物をいくつもつくるようなことだし。

だけど、同じテーマや作風を継続するってそういうことだろ。

ここが一番難しい。テーマや手法を見つけて、実際にいけそうと判断できて、アレを撮るぞ現像するぞとやるわけだけど、数回続くと鋳型に流し込む鉄になってる。それでも、この方法論なら成功するという気持ちが強いから無意味な量産に気づきたくなくっている。で、そのうち嫌でも気づいて思い知らされると。

気づきたくないのかよ(笑)。

そりゃそうだよ。誰かのパクリなら飽きておしまいだろうけど、自分が発見したり熟成したものなんだから、うまく行く手応えを失いたくないよ。

でも気づいて悩むのか。

継続テストを続けて記事にしているDタイプマイクロ105mmの試験を兼ねて散歩に持ち出したわけですよ。なんとなく知ってるけど知らない場所に強引に出かけるのが好きで撮影していたら、「Past Light」の別の展開に気づいちゃったと。それがこれ。


うん、違うな。

これは「Past Light」を撮ろうとは思っていなくて、面白い光景に出会ってまさに犬も歩けば棒に当たるだと喜んで構図を決めたんだよね。で、シャッター切った直後に「Past Light」だと気づいた。「Past Light」は福島浜通りの被災地からはじまって、その後は砂の景色に拡大してた。まさか日常を撮影する方法や現像法とは考えもしなかったんだ。

日常っていうのもあるけど、雰囲気違わない?

そうそう。違うし、言いたいことも微妙に別なんだよね。でも一貫して光についての考察っていうか、光のスタイルについてのおいらなりのひとつの答え。

実際のとこ、「Past Light」って何をどうやってるの?

平面的な構図が多いし、単調な感じを出そうとしているし、構図としては抑揚をなくして、光の強弱を光の濃淡で解釈するという自分にしかわからないさじ加減。で、失敗作にするかこれもアリにするか考え中のがコレで、やってることは一目瞭然かも。


これってお得意の強烈ストロボとフレネルレンズ とか使ってるわけ?

そうとも限らないし、あまりに遠景はストロボ光は届かないし。でもまあ、そういうことだよね。さっきの散歩写真は機材の支度とかしないで出かけて撮影しているけど。

企業秘密かよ(笑)
話は戻るけど、なぜ光を強くなのか明るくなのかした作風をつくろうとしたの? しかもテーマにもなっているし。

カラーの表現をどうするかが根本問題で、おいちゃんも知っての通りおいらは20代からずっと色をどうするか悩み続けてきた。フィルムを使っていた時代のカラーはフィルムの銘柄と印画紙というか暗室の化学反応で決まるというかで、やれることがあまりに限定されて、いろいろやったけど満足できなかった。

ほんとモノクロばっかりだったよね。カラーはお仕事とか記念写真とかで。

デジタルでRAW現像できるぞとなったとき、いちばん最初に手をつけたのがカラーをどうするかの実験だった。でもなかなか答えがみつからなくてモノクロを深めるほかなかったんだけど、デジタルでやってると数値で濃度や明暗が分析できて、モノクロの黒っぽさの原因がわかってきたと。

だけどさっき福島の頃も黒くてドロドロ化してたって言ってたよね。

プリントしてみるとそうでもないけど、ディスプレイで見るとほんと黒くてドロドロ。フィルム時代の他の人を含めてそういうものだったし、トーンを出し切るゾーンシステムみたいな考え方を追求するとけっこうその方向に陥っていくんだなコレが。で、やーめたやめたと嫌気がさした。

それでカラーの話をどうなった?

数値で濃度を見ていくと、カラーとモノクロは同等なんだよね。つまり彩度が失われると重苦しくてヘビーでドロドロ化する。あるいはモノクロでトーンの追求やら迫力やら求めると、このままカラーに戻したときグロいまでにケバケバしいし破綻している。そこでモノクロもカラーも明るく、あっさりさせていったらどうなるか本能的にいろいろやった結果だな。そのうち暗さで抑揚をつけるのではなく、白とびぎりぎりかつトーンが残る明るい領域で抑揚をつけたと。

ドロドロしてるならあっさり味にすればいいやと。ラーメンの好みみたいだな。

しかしドロドロに慣れてると、あっさり味で成立しているのか不安になる。まずモノクロで体を慣らして、約一年半くらいかなあカラーでやれる体質になったのは。で、応用の「Past Light」に至ったのは、写真をすっかりデジタル化させてから10年かかってるという。

なのに「Past Light」とかでさえ、またまた無為無策で量産してる危険性を感じると。

あっという間なんだよ、気づきから量産への時間なんて。2、3ヶ月やれば惰性の時期がやってくる。そこで、少しずつずらしている。たとえばコレとか。

いっしょだろ、と言われたら「すみませんね」なんだけど。
量産できるというのは、撮影と現像するための要件がすべて自覚できていて繰り返している段階なんですよ。だから惰性を感じたら、要件のうち何かひとつを別物にする。ただし、どうしても外せない要件は残す。

その写真ははじめて見たな。福島からの「Past Light」とも違って、空の感じはけっこう強く出してない? あと砂浜の感じも別ものじゃない?

空は、この日の天候がこうだったわけ。ただ、そのままでいいかは迷った。これでいいのかどうか、ほんとうのところはわからない。おいらがわからないんだから、他の人は好き嫌いはあっても良し悪しは判断できない。空はこれまでの「Past Light」の定石をはずした結果だし、砂浜はスタジオにつくりこんだセットみたいな雰囲気を出して風景撮影から遠いものにしようとしている。

たしかにスタジオに砂を敷き詰めて、海藻とか置いて、背景はでっかい写真か何かを置いているような雰囲気だ。

定石をはずしたといっても、最初から「Past Light」にしようと目論んでる。でも、これまでと少しはずした「Past Light」にしようって。散歩途中の壁写真とも方法論が違う。空に艶感を出したうえで現像時に彩度を調整して、手前の砂浜なんかはセットっぽい見かけにして、50年代くらいのカラー初期の雰囲気というか古いハリウッド映画的なものとかにしようと。

あー、かなり計画的だ。ガッチガチでもある。

現場で被写体を見つけて、その場で計算してガッチガチだな。

その場の計算通りにうまく行くものなの? やればできることなのか?

うまく行かないときも多いよ。計算ずく以前に、ケアレスミスすることだってある。大切なのはいつものやらないことを撮影しておくのと、明らかなケアレスミスを持ち帰って現像してみるってこと。そのカットは使い物にならないかもしれないけれど、意図的に外したカットや失敗カットをなんとか作品化しようと現像しているうちに重大なものに気づくんだなこれが。

具体的にどんな気づきがあった?

たとえば、これかな。とにかく風と飛砂がものすごい日で、ファインダー覗くのも大変、ライブビューなんて見つめていられない。ピントを合わせるまえに一旦退去しようとしてたときうっかりシャッターを切ってしまった。だから目の前の杭にピントがぜんぜんきてない。

その場で消去してもいいし、現像しないままでもいいカットなんだろうけど、ものは試しでまじめに画像化してみた。やっているうちにピントがきていないよさがはっきりしてきて、完全なモノクロではピントはずれの意図がはっきりしないからパートカラーっぽく色を残した。で、けっこう評判がいい。

背景の波にはピントがきてるね。

いつでもこの方法論を使えるというものじゃないのはわかってる。でも、カタチではなく光や心象を語りたいときピントがくるべきものをボケたままにして、すっとぼけた感じで背景にディティールがくるとかアリだなと。珍しくない手法だけど、ずっと忘れていたんだ。さっきの写真では似た構図だけど、物体で何か言わせている点やワーキングディスタンスから同じ方法論は使えない。

ピントがはずたカットはテーマでも作風でもなくて、そこまで昇華された方法論ではないけれど予備軍だし、手法の選択肢として持ち駒になった。

なるほどね。とにかく全部持ち帰って、駄目もとでいろいろやって噛み締めろと(笑)。そこまでスタイルや方法論にこだわるのって、なぜなの?

いよいよ本題ですか(笑)
カメラに写真を撮ってもらうとか、お手本にする誰かの写真を真似てもぜんぜん楽しくないし、他人がどう評価するとか関係なく短い人生好きなようにしたいからだな。自分の写真は価値観のまんまのものにしたいわけ。歌手って音程があっていることより、必要な範囲で音程があったうえで、俺節っていうか独自の旨味とか雑味が貴重じゃないですか。

でも、本音では失敗したくないでしょ。確実に認められるほうがいいと思う瞬間あったりする?

それが、あんまりないんだな。フィルムシミュレートモードとか、誰それ流プリセットとかも恥ずかしさと不自由さが先にきて拒絶反応しかない。写真なんてそもそも誰がシャッター押しても絵と違って似たものになるんだから、歌でいうところの俺の節回しとか俺の声質とかがなかったら意味ないと思うよ。

© Fumihiro Kato.
Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited. All Rights Reserved.